児童発達支援をご検討の方へ
健診で発達の遅れなどを指摘された方や、保育園や幼稚園の集団生活につまずきを感じるお子さん。
また子育てのしづらさを感じる保護者の方に、それぞれのお子さんの発達に応じた支援をします。お子さんに無理なく、楽しく過ごせる環境で、それぞれのペースを大切に療育をします。お子さんの行動をしっかりと分析して保護者の皆さんの子育てが楽しくなるようにお手伝いします。
サービス内容

●児童発達支援では、障がいのあるお子さんや発達の気になるお子さん等に、保育園や幼稚園のような集団生活の場を提供しています。
その中で日常生活における基本的な動作の指導、機能訓練等を行ないます。
●利用対象者は、療育の観点から個別療育 集団療育を行なう必要が認められる、小学校就学前(6歳)までの児童です。
特に「療育手帳」や「身体障害者手帳」をお持ちでなくても、必要と認められれば利用することが可能です。
1日の流れ
- 登所
- 自由あそび
- 10:30
- はじまりの会 朝のあいさつ・朝の歌・出席確認・絵本や手遊び・今日のおはなし
- 10:45
- 活動① 製作・絵画・調理など、机上で椅子に座って取り組みます。
幼稚園や保育園、小学校などで着席することを想定しています。
指先の微細運動や、集団への指示への理解、感触などそれぞれの得意を伸ばすように支援します。
- 11:15
- 活動② リズム遊び、サーキット、体操をはじめとする身体を使った活動を行ないます。
季節によっては、お散歩、プール、公園にお出かけもします。
- 12:00
- お弁当 楽しくみんなでお弁当を食べることを意識しています。
偏食の気になるお子さんも少しづつ、それぞれのペースに合わせて食べられるものを増やせるように支援します。
併せて食事における所作を身に着けます。
- 12:40
- 午睡 普段のリズムを崩すことのないように、午睡の必要なお子さんは1時間から1時間30分ほどお昼寝をします。
お昼寝の習慣のないお子さん、体力のあるお子さんは午睡しません。
(個別療育・自由遊びなどをします)
- 14:00
- おやつ
- 14:30
- 降所準備
- 14:50
- かえりの会
- 降所
- 順次降所
支援のポイント
総合的な支援
●児童発達支援では、 将来、日常生活や社会生活を円滑に営めるように、「①健康・生活 ②運動・感覚 ③認知・行動 ④言語・コミュニケーション ⑤人間関係・社会性」
この5領域の視点をふまえたアセスメントを行ない、生活や遊び等のなかで発達を促すためにそれぞれのお子さんに合わせた支援を行ないます。
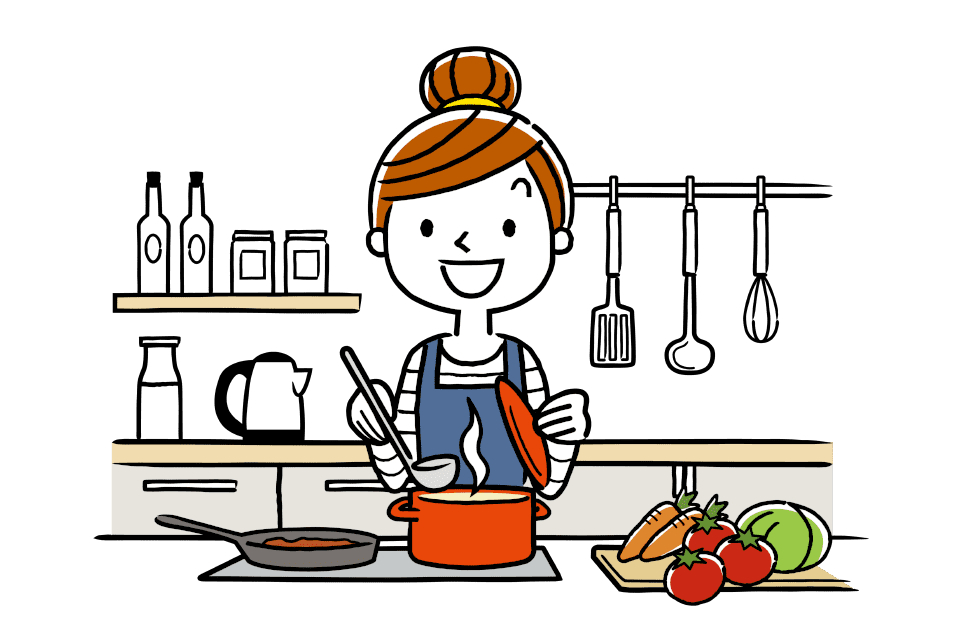
- ①健康・生活
- 毎日を元気に過ごすためのリズムや生活習慣を整え、食事や排せつ、身の回りのことなど、自分でできる力を少しずつ育てていきます。

- ②運動・感覚
- 体を動かす楽しさを感じながら、姿勢や動作がスムーズになるように取り組んでいます。また、見たり触れたりする感覚を大切にしながら、バランスよく発達できるよう支援します。
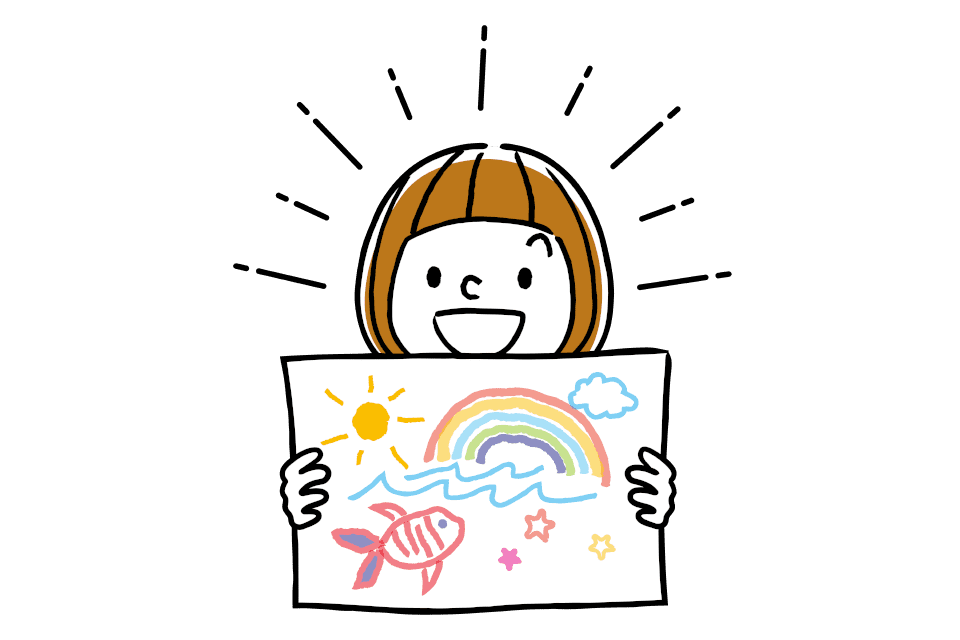
- ③認知・行動
- 「見る」「聞く」「比べる」などの力を育て、時間や数、場所の感覚などを遊びの中で自然に身につけられるように支援します。また、自分の思いを行動に移す力も育てていきます。

- ④言語・コミュニケーション
- 「伝えたい」「わかってほしい」という気持ちを大切にしながら、言葉やジェスチャー、視覚的な手段など、その子に合った方法でやりとりする力を育てます。
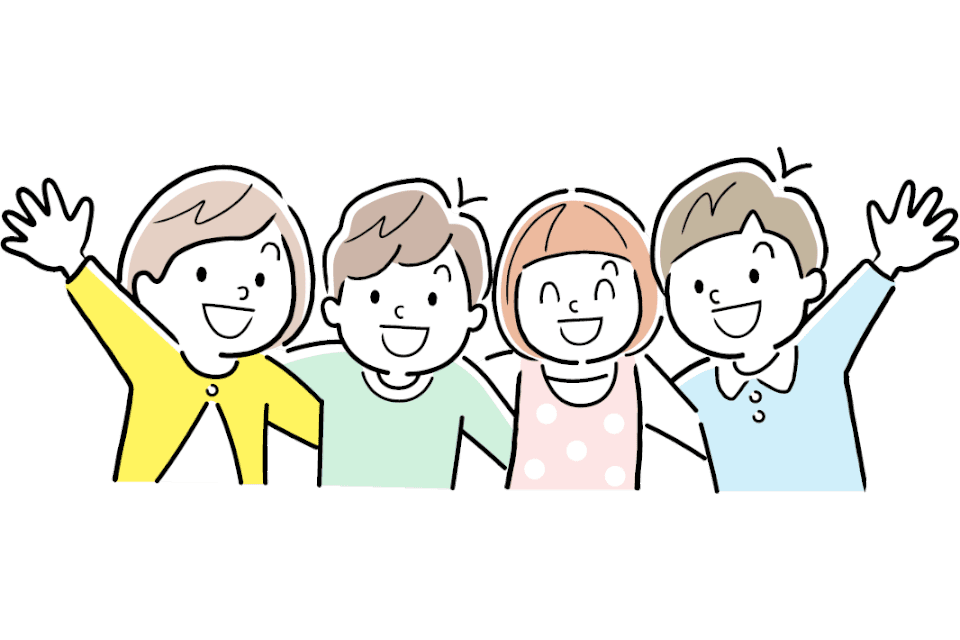
- ⑤人間関係・社会性
- 友だちや先生との関わりを通して、人と一緒に過ごす楽しさやルールを学びます。集団の中で自分の気持ちを伝えたり、相手を思いやったりする経験を重ねていきます。
専門的な支援
5領域の総合的な支援に加え、専門職による機能訓練や心理指導など、5領域のうち、特定(または複数)の領域に重点をおいた支援を集中的に行ないます。
支援内容
- ①本人支援
- ・日常生活における基本的動作及び知識技能の習得
・生活能力の向上を図る為に、それぞれのお子さんの成長を促す
- ②移行支援
- 障がいの程度にかかわらず、可能な限り地域の保育・教育等を受け、同年代の子どもと仲間になって、共に成長できるように支援
- ③家族支援
- ・障がいや発達についてお子さんを家族として受け止め、ありのままを肯定
・本人の育ちを支え続けられるように家族を支援
- ④地域支援
- ・お子さんが地域で適切な支援を受けられるように関係機関等と連携
・地域の子育て支援力を高めるネットワークを構築
対象者
●集団療育及び個別療育を行なう必要があると認められる、 未就学の障がい児
※医学的診断名または障がい者手帳を有することは、必須要件ではありません(医師の療育が必要であるという意見書で可)。
対応事業所
-
青空
(三芳町)
-
ふじみのそら
(富士見市)
-
にじのそら
(上尾市)
-
にじのそらきっず
(伊奈町)










